土地・電力・通信、3つ揃う場所はそう多くない
現場から見た“データセンター適地”の探し方と評価の視点

ファン1個で年間数十万

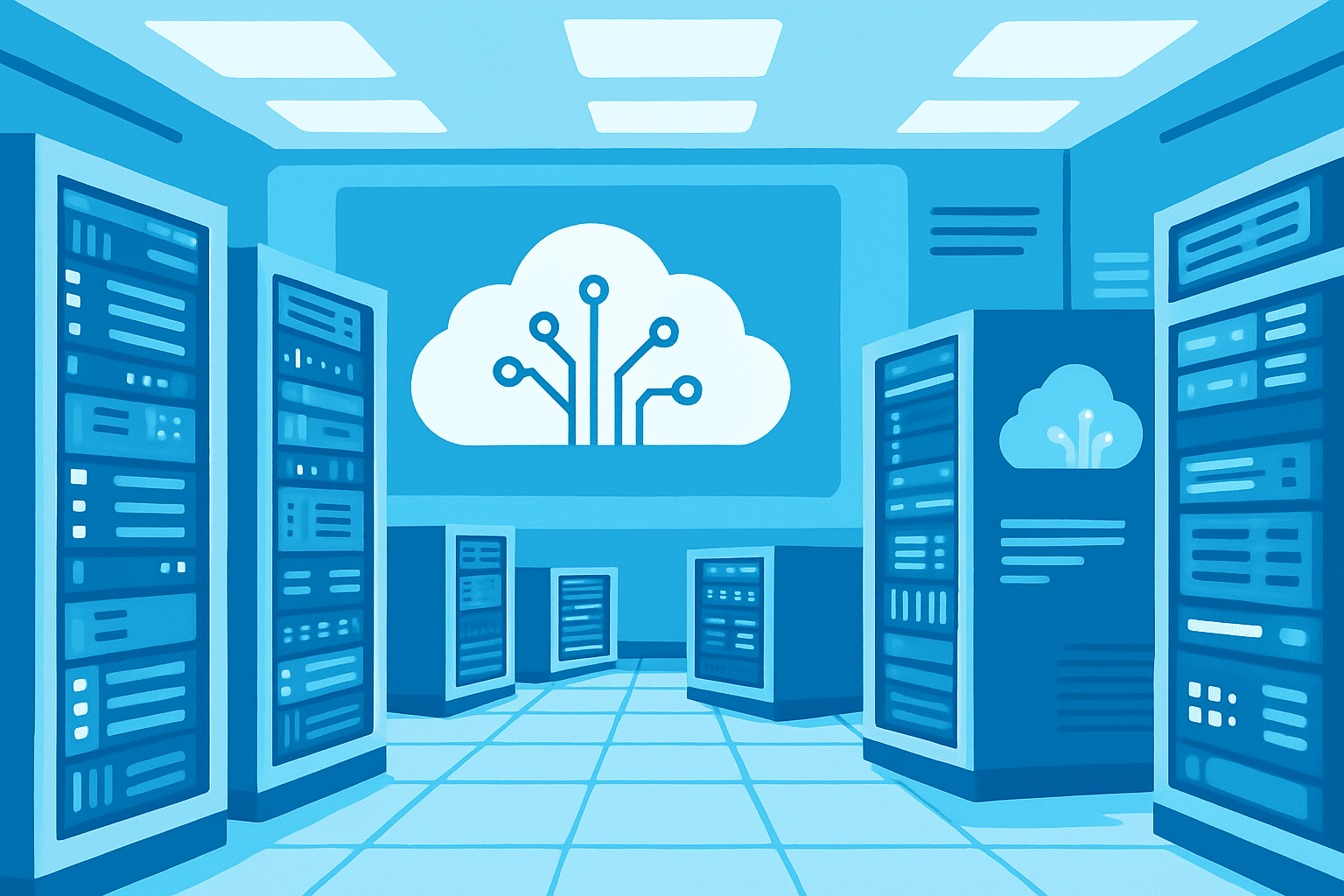
高効率なデータセンター運営を目指す企業にとって、電力効率や空調制御などの「大きな仕組み」への投資は常識になりつつあります。しかし、多くの現場で見落とされがちな要素──それが“消耗部品”の存在です。ファン、フィルター、バッテリー、電源ユニットなど一つひとつは地味な存在ですが、放置すればそれらがボトルネックとなり、数十万単位の損失を生む原因となるのです。この記事では、こうした“地味だけど効く”運用改善の視点から、消耗部品の重要性と保守戦略の再構築を提案します。
データセンターにおけるサーバー冷却や安定稼働を支えるのが、ラック内に内蔵されたファンや、機器全体の通風を管理するフィルター、さらにバックアップ電源用のUPSバッテリーなどの「消耗部品」です。これらは、静かに、しかし確実に寿命へと向かいます。
例えば、1台のサーバーに搭載されたファンが摩耗し始めると、同じ回転数でも風量が低下し、冷却効率が悪化します。温度上昇を感知したサーバーや空調設備は、過剰に冷却を行うようになり、結果として全体の電力使用量が増加します。この負荷上昇が続けば、1台のファンの劣化が原因でラック全体の平均温度が2〜3℃上昇し、空調消費電力が5〜8%増えるという事例もあります。
加えて、劣化ファンから発生する異音や振動は、筐体内部の他部品にも微細なダメージを蓄積させ、システム障害の引き金にもなりかねません。このように「たった一つの部品」が、冷却コスト、故障対応、人件費の3重苦をもたらす可能性があるのです。
多くの現場では、消耗品は「壊れたら替える」「止まってから呼ぶ」という後追い型の運用が主流です。ですが、このスタイルでは突発的な障害対応に追われ、かえって高コストな運用になってしまいます。
近年では、機器に取り付けられた温度センサーや回転数モニター、電流値のログを活用し、消耗部品の劣化兆候を早期に捉える「コンディションベース保守(CBM)」が広まりつつあります。たとえばファンの回転数と電流値を監視し、一定の変動幅を超えた段階で「交換アラート」を出す仕組みは、特別なセンサーがなくても、既存設備のログ活用だけで導入できます。
このような仕組みを導入すれば、年2回の定期交換よりも劣化進行に応じた“無駄のない交換”が実現でき、部品の使用寿命を最大限引き出しながらも、故障リスクは最小限に抑えられます。また、これにあわせて技術員のマニュアルも「パーツ単位の健康診断」に進化させる必要があります。温度差、騒音、振動など、定量的な指標で交換判断する文化が求められます。
部品管理でもう一つの見落とされがちなポイントが「在庫戦略」です。消耗品は安価だからといって最小限しか持たないスタンスは、障害時の迅速対応を妨げ、想定外のダウンタイムを引き起こすリスクがあります。特に海外製機器などは、発注から納品まで1〜2か月かかることもあり、突然の故障時に対応不能となるケースが散見されます。
効果的な在庫管理のためには、まずは使用頻度と交換サイクルに基づく「予測在庫モデル」の構築が必要です。たとえば、冷却ファンや電源ユニットなど年1回以上交換が発生する部品に関しては、必ず拠点ごとに“即応在庫”を1〜2セット確保。逆に、レアな仕様の部品は集約倉庫で一括管理し、クロスロジスティクスで当日配送できる体制を整備するのが理想です。
また、在庫部品のバーコード管理や、クラウド型の在庫台帳の導入により、属人的だった在庫把握を脱却し、保守対応の標準化が図れます。さらに、メーカーや商社との連携で“予備在庫を取り置きしてもらう契約”を結ぶ企業も増えており、BCP(事業継続計画)視点でも有効です。
かつてのデータセンター運用は「止まらないこと」が最優先でしたが、これからは「効率よく止めずに回すこと」が求められています。その中で、見落とされがちだったファン1個、フィルター1枚、UPSバッテリー1本といった部品が、今や運用効率を左右するキーファクターに変わりつつあります。
こうした流れに対応するには、「部品寿命を見える化する仕組み」と「交換に備えた即応体制」、そして「定量評価に基づく保守文化」の3点が欠かせません。これらが整えば、保守の“ムダ”や“抜け”をなくし、トータルで見たときのTCO(Total Cost of Ownership)を劇的に下げることが可能になります。
目立たないけれど確実に効く改善。それこそが、これからのスマートDC運用の礎となるのです。