“止めない工場”を実現するには?
ロボットの予防保全・異常予兆検知の最前線

“止めない工場”を実現するには?

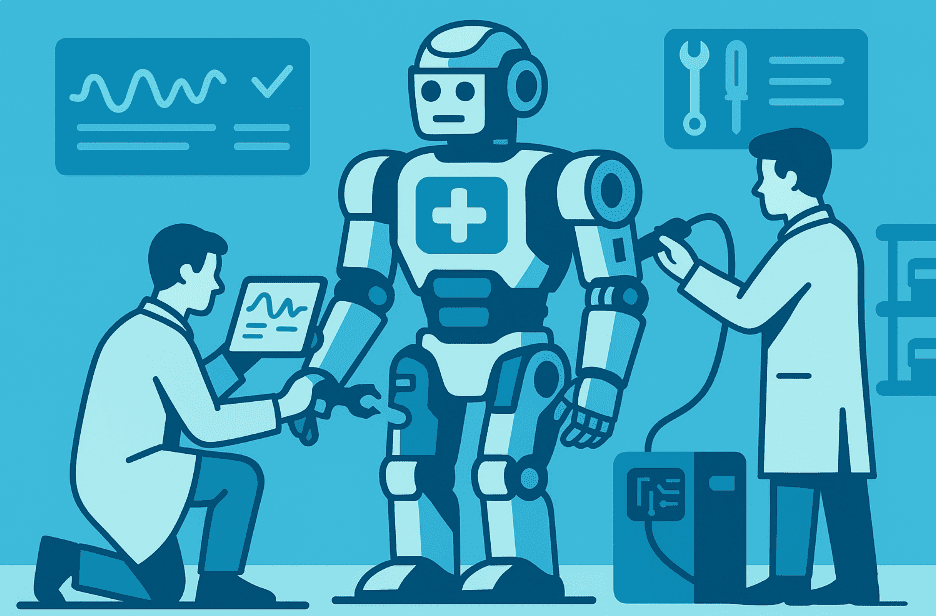
自動化された製造現場では、産業用ロボットが単なる作業装置以上の存在となっている。24時間体制の工場で、溶接・塗装・搬送・組立といった工程を担うロボットが一台でも停止すれば、全体のラインが一時停止し、計画損失が即座に発生する。
その損失額は、規模によっては1分あたり数十万円に及ぶこともある。加えて、復旧対応に追われる現場スタッフや管理者の精神的コストも看過できない。
そんな中、「ロボットを止めない」ための技術として注目されているのが、予防保全と異常予兆検知の仕組みだ。
従来、ロボットの保守は「定期点検+突発対応」が主流だった。しかしこのアプローチでは、突発故障を未然に防げないという限界がある。
ここで注目されているのが、振動センサやトルクセンサを用いたロボット状態のモニタリングである。アームの関節やベース部にセンサを組み込み、動作中の微細な異常(振動の変化や負荷の偏りなど)をリアルタイムで検知する。
加えて、ログとして蓄積されたセンサデータをAIが解析し、「過去にはこの振動パターンで○○日後に停止した」というようなパターン認識を行うことで、異常の“予兆”を捉えることが可能になる。
すでに、複数のメーカーがこうした「予知保全モジュール」を開発。ロボットメーカー各社の純正オプションとして搭載されはじめており、導入コストもかつてに比べ大幅に低下している。
現場で実感される最大の変化は、保守対応が「計画できる」ようになったことだ。
これまでは、突発故障に備えて常に予備部品や人員を待機させておく必要があったが、予兆を捉えられるようになれば「あと3週間後にこの関節モーターの交換が必要」といった対応計画が立てられる。
これはつまり、稼働率を落とさずにメンテナンスを行えるということ。現場の安定性を高めるだけでなく、余計な在庫部品や対応人件費を抑えるという経営的メリットにも直結する。
とはいえ、「異常検知を始めたい」と考えたとき、単にセンサを取り付けるだけでは成果には結びつかない。
① 見たい故障の“種類”を明確にすること。
関節部の摩耗なのか、内部の冷却系統の異常なのか。狙う対象によってセンサの種類や設置位置、解析手法は大きく異なる。
② “学習期間”を見越して導入すること。
AIによる予兆検知には、正常時/異常時のデータが一定量必要になる。学習フェーズに数週間〜数ヶ月かかることもあるため、短期的なROIだけで判断しないことが重要だ。
③ 現場スタッフとの“運用設計”を忘れないこと。
いくら高精度な分析が可能でも、それを現場で使いこなせなければ意味がない。データの見せ方、アラートの通知方法、対応マニュアルの整備など、“技術と人”をつなぐ工夫が欠かせない。
予防保全・異常予兆検知の技術は、今後「当たり前の機能」としてあらゆるロボットに標準搭載されていく流れにある。
すでに大手製造業では実証導入が進んでおり、中堅・中小企業でも「一部のロボットだけ」「PoCとしてスタート」する事例が増えている。
設備が止まってから慌てるのか、止まる前に手を打つのか。
それは、単なる運用の問題ではなく、“未来の生産性”を左右する経営判断だ。