効率運用の第一歩は使ってないサーバの整理
データセンター効率化はサーバ棚卸から始めよう

“ロボット修理難民”にならないために

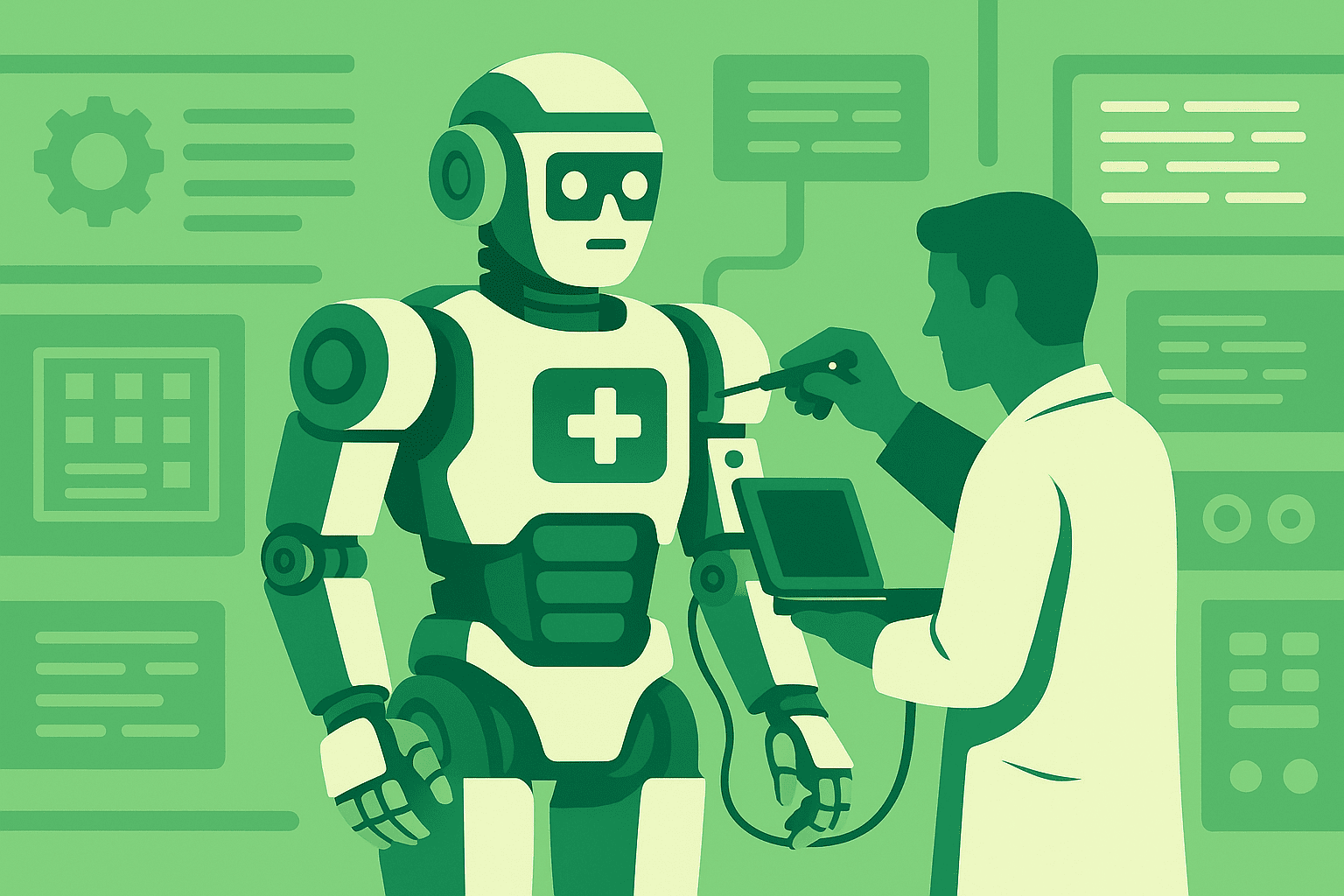
製造業の自動化が進むなかで、多くの現場でロボットの導入が進みました。しかし導入から数年経ち、今あらためて注目されているのが「サポート切れ=修理難民化」のリスクです。とりわけ中古ロボットや海外製ロボットにおいては、このリスクが表面化しやすく、止まってから慌てるケースが後を絶ちません。
この記事では、ロボット修理難民にならないために必要な視点を、EOL(End of Life)対策やリバースエンジニアリング、代替部品供給の実情とあわせて解説していきます。
ロボットを導入する際、多くの企業が本体価格や稼働性能に注目しますが、保守体制の持続可能性まで見通しているケースは決して多くありません。特に中古品や並行輸入された海外機の場合、製造元のサポートがすでに終了している、もしくは最初から存在しないケースすらあります。
これが、いわゆるEOL(End of Life)問題です。メーカーが部品供給やソフトウェア更新を打ち切ることで、故障時の修理が不可能になり、現場は突如として“ロボットレス”な状態に陥ります。生産性はもちろん、取引先への納期や品質保証にまで影響することになりかねません。
こうした問題に対して、注目されているのが「リバースエンジニアリング(逆設計)」による部品再生です。すでに製造終了した部品でも、現物の形状や素材特性を3Dスキャンや材料解析によって解析し、代替品として製作する技術が進化しています。
ただし、すべての部品がこの手法で再生できるわけではなく、安全認証が必要な部分や、電子制御基板のように複雑なロジックを含む部品については、実用化が難しいケースもあります。そのため、どの部品が“リバース可能”かをあらかじめ把握しておくことが、事前の備えとして重要になります。
代替部品の供給においても注意点は多く存在します。たとえば、同型機の中古市場からの調達や、OEMメーカーによる汎用互換品の流通はありますが、品質や耐久性がまちまちで、純正品と比較して信頼性に不安が残るケースも見られます。
また、海外製ロボットにおいては、言語・規格の違いによる調達ハードルや、輸送のタイムラグによる修理遅延など、部品到着まで数週間を要することも珍しくありません。
それでは、ロボットのサポート切れリスクに備えるには、どのような視点が必要なのでしょうか?以下に実践的な対策を3つ挙げます。
導入から10年を超えてなお、安定稼働しているロボットは数多く存在します。そうした現場には、必ずと言っていいほど“備え”があります。すなわち、サポート体制の見極め、代替部品の確保、そして独自のメンテナンス戦略です。
ロボットは精密機械であり、製造ラインの中核を担う重要資産です。計画的な保守とサポート体制への目配りこそが、設備投資を「持続可能な力」へと変える第一歩なのです。