データセンター運用における電源効率とPUE改善の実践例
データセンターの“電力ロス”はこうして減らす

効率運用の第一歩は使ってないサーバの整理

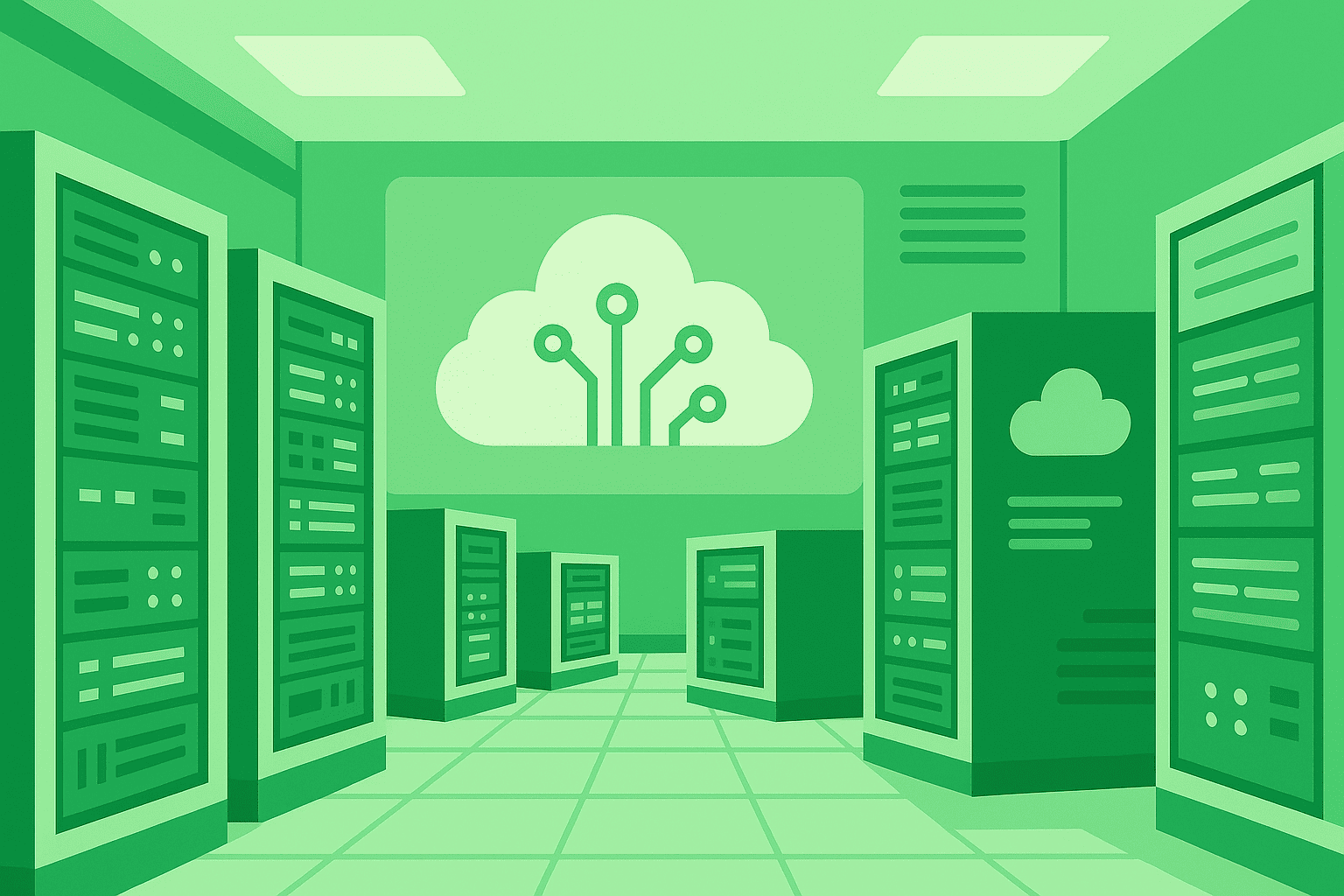
データセンターの効率化を語るとき、多くの企業がまず思い浮かべるのは冷却や空調、ラック設計や電源管理といったインフラの最適化かもしれません。しかし、もっと本質的で即効性が高く、しかも費用対効果に優れた施策があります。それが「サーバ棚卸」です。
稼働しているように見えるサーバ群の中に、実はもう利用されていない、あるいは誰が何に使っているのかわからないサーバが潜んでいるケースは少なくありません。これがいわゆる「シャドーIT」や「ゾンビサーバ」です。
業務から退役してもシャットダウンされずに稼働を続け、電力と冷却リソースを無駄に消費している。こうしたサーバ1台が年間に消費する電力量は数百kWhにのぼり、複数台が積み重なると、年間数十万円単位のコストが静かに流出していることになります。
最初のステップは、現場の物理サーバと仮想サーバのリストアップです。資産台帳に記載されている内容と実際の構成を突き合わせ、管理ラベルが剥がれていたり、ネットワーク構成図に記載されていない装置がないか、徹底的に洗い出します。
多くの企業でこのフェーズが「面倒だから後回し」になりがちですが、逆にここをやらないとDX投資のROIが正しく見えません。
棚卸の過程では、各サーバの稼働目的と現在の利用実態を確認します。「昔の社内アプリが動いてるから消せない」というサーバもあるでしょうが、そこにはリプレースや仮想化の余地があります。システム部門とアプリ担当部門の連携が必要ですが、保守ベンダー任せにせず、内部主導での確認こそが中長期のコストダウンに直結します。
不要なサーバのシャットダウンと同時に、利用頻度が低く、負荷の低いサーバを統合・再配置する動きも進めるべきです。
特にVM環境やコンテナ環境を導入済みの企業では、遊休リソースの統合によってラック数や電源容量、空調負荷の削減に直結します。再配置に伴い、ラック構成やケーブリングの最適化も並行して実施することで、作業効率と可用性の向上も見込めます。
単なるコストだけでなく、情報セキュリティ上のリスクも大きな問題です。管理対象外のサーバに古いOSやミドルウェアが放置されているケースも少なくありません。
OSのサポート切れやパッチ未適用のまま外部接続されていれば、サイバー攻撃の入口になりかねません。棚卸は「資産管理」だけでなく「脆弱性の棚卸」としても機能し、セキュリティ対策としても効果的です。
一度棚卸をしただけでは、数か月で現場は元に戻ります。業務の変化に応じてインスタンスやサーバは増減します。だからこそ、定期的な見直しサイクル(半年~1年)と、棚卸を伴う業務申請・記録のルール化が必要です。
DCIM(データセンターインフラ管理)やITAM(IT資産管理)ツールの導入も、人的リソースに頼りすぎず継続性を確保する上で重要な手段となります。
多くの企業が「効率化」という言葉の下、空調設定の微調整やラック内気流の最適化といった技術に注目しますが、最も“効く”効率化は「止めること」です。
止められるサーバを止める。統合できる環境を統合する。棚卸はその第一歩です。